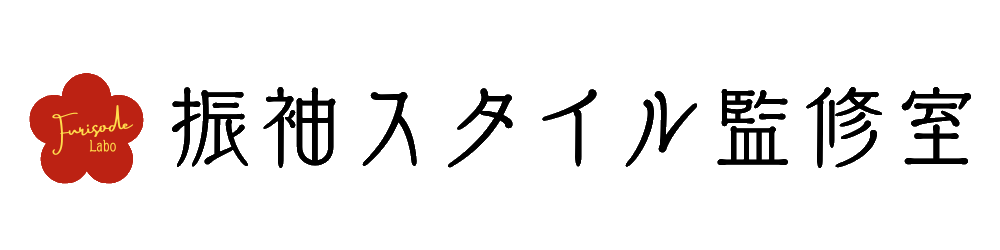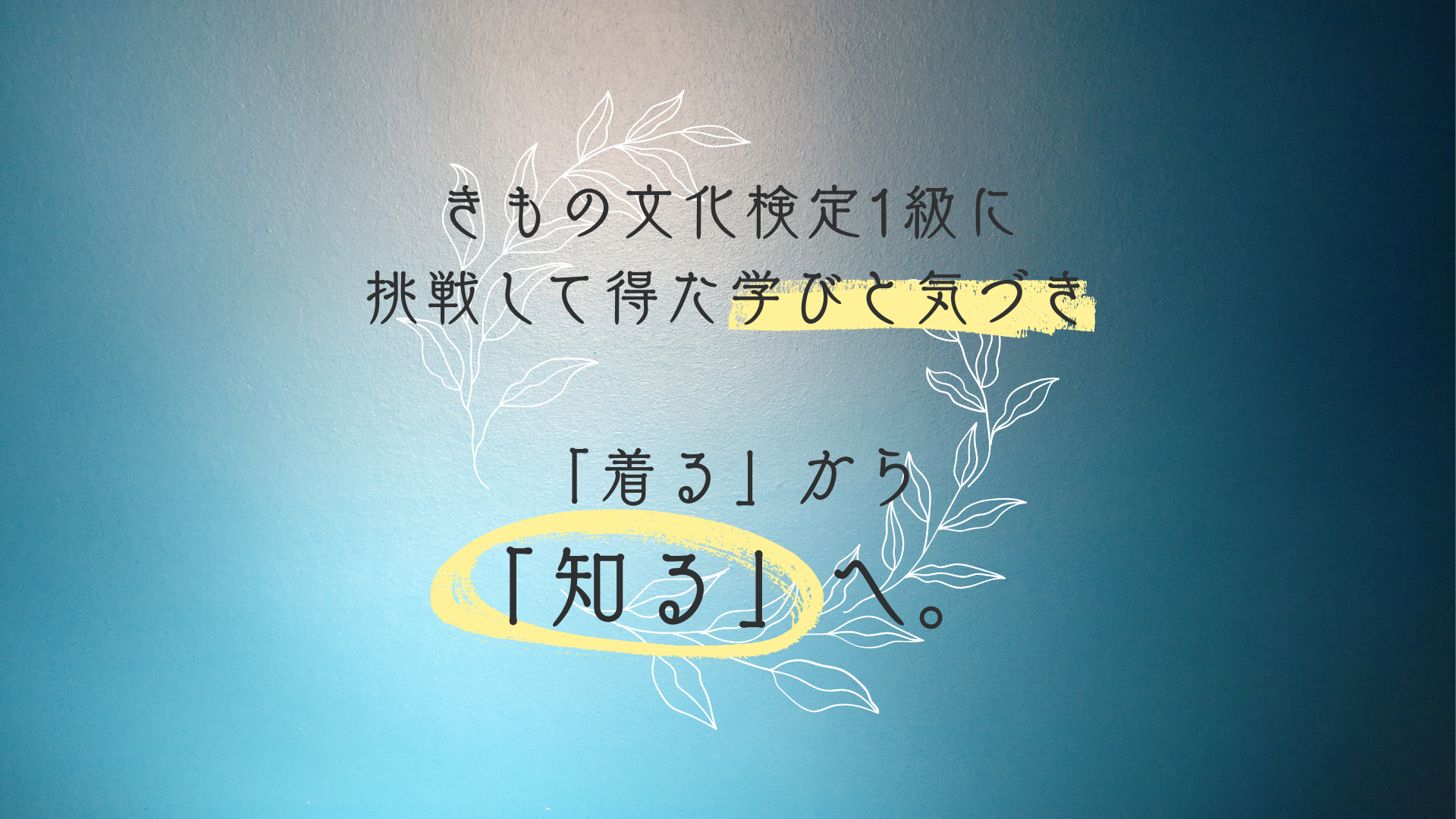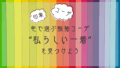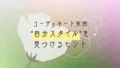きもの文化検定という検定名、あなたはどんな印象を持つでしょうか?
私がこの検定に出会ったのは、着付け教室に通い始めて間もないころ。きものの色柄や着物の形に惹かれるうちに、「もっと深く、きもののことを知りたい」と思うようになったのがきっかけでした。
この記事では、1級受験に向けた勉強の日々や、得られた学びについて綴っています。
きもの文化検定を受けようと思った理由
「なぜ着物は右前なの?」
「十二単から現在のきものまで、どんな変遷があったの?」
そんな疑問が芽生えたことが、きもの文化検定受験の第一歩でした。
「もっと深い意味を知ってコーディネートしたい」「背景を知れば、着るのがもっと楽しくなるかも」と思うようになり出会ったのが、きもの文化検定。
着物の歴史や文様、素材や技法など幅広く問われるこの検定は、まさに「知る」楽しみを味わえる道しるべのように感じました。
私は、より深くきものの文化を理解したいという思いから、私はきもの文化検定の受験を決意しました。
misakoはきもの文化検定1級に初回受験で合格しました。2021年4級、2022年3級、2023年2級、2024年1級合格。
合格率10%。何度も挑戦する人が多い1級試験
きもの文化検定1級は、合格率が毎年10%前後と、決して簡単な試験ではありません。何年もかけてチャレンジしている方も多く、自分のペースで取り組める「大人の学び直し」にぴったりの検定だと思います。
検定の内容は多岐にわたり、
・模様や色の意味
・織・染の技法
・着物の手入れ方法
・時代ごとの装いの変遷
・行事との関わり……など、どれも奥深く、勉強しがいのあるテーマばかりです。
ひとつひとつの知識を学んでいくうちに、
「知らなかったことを知るって、こんなに楽しいんだ」と感じることの連続でした。ただ「着る」だけではない、自分の中に確かな軸が生まれていくのを感じました。
困ったのは、過去問が手に入らないこと
実際に学習を始めてみて感じたのが、「過去問がとにかく手に入らない」ということ。
中古品は出回る数が少なく、定価の2〜3倍で出品されていてもすぐに売り切れてしまいます。
私は4級受験時の時から、数年かけて過去問を集め、過去問を繰り返し解きながら、図書館で本を借り、少しずつ資料を集め、1級合格に向けて自分なりのノートを作りました。
組織や産地など、覚えにくかったり難しい内容も図とセットでわかりやすくまとめるよう心がけました。
同じように頑張る方へ。ノートコピーをお分けしています
同じように「資料がなくて困っている」「独学で勉強している」という方の役に立てたらと思い、
私の1級対策ノートのコピー、2級対策ノートのコピーを【メルカリ】と【ココナラ】で販売しています。
ありがたいことに、
「テーマごとに整理されていて復習しやすい」「図解つきで、イメージが頭に入りやすい」とご好評をいただいています。
- きもの文化検定2級ノートコピー ココナラでのPDF販売
- きもの文化検定1級(仕立て・手入れ(悉皆))ノートコピー ココナラでのPDF販売
- きもの文化検定1級(産地)ノートコピー ココナラでのPDF販売
- きもの文化検定2級/1級ノートコピー メルカリでの紙媒体販売
「学ぶこと」が、きものをもっと楽しくする
この検定を通して、私は「きものを着る楽しさ」が「知る喜び」へと変わっていきました。
きもの文化検定は、単なる資格ではなく、「きものを一生の趣味にしたい」という方にとって、
とても価値あるステップになると思います。
あなたの挑戦を、心から応援しています。もし今、勉強につまずいたり、不安を感じている方がいたら…大丈夫です。何度でも挑戦していいんですし、学んだ知識は必ず自分の力になります。
「きものがもっと好きになりたい」――その気持ちを、ぜひ大切に。
一緒に、学びを楽しみましょう。